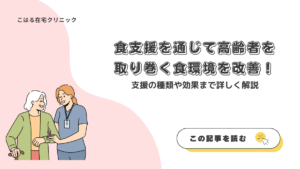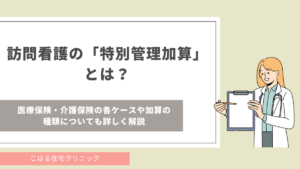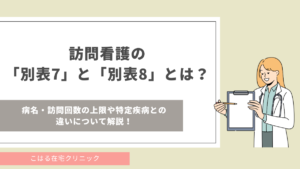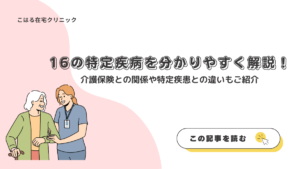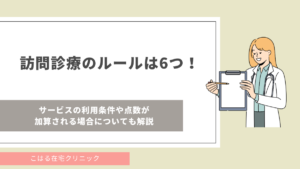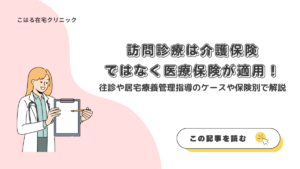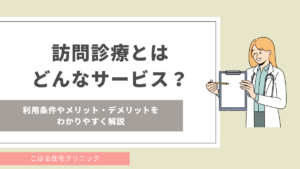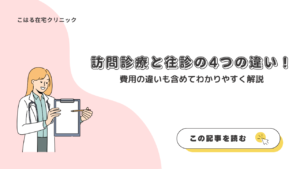訪問診療に興味があるものの、費用面で不安を感じる方もいるのではないでしょうか。
訪問診療の費用は、通院よりも高くなる傾向がありますが、交通費や待ち時間など含めてトータルで考えると安くなるケースもあります。この記事では訪問診療の費用相場や通院・入院との比較とともに、費用が高額になった場合の補助制度について解説します。
訪問診療の費用相場
月2回訪問診療を受けた場合、1か月の負担金額の目安は以下の通りです。
- 1割負担 約7,000円
- 2割負担 約14,000円
- 3割負担 約20,000円
実際の金額は訪問回数や検査の有無など診療内容によってさまざまです。同じ内容でも公費や介護保険の有無、年齢や所得金額によって医療費の計算方法が異なるため、人によって負担金額が違う場合があります。
ただし、いずれの場合も高額になった場合は高額医療費助成制度や、医療費控除の対象となり、所得に応じた補助を受けられます。
訪問診療と「通院」の費用面での違い
厚生労働省の「医療保険に関する基礎資料」(令和3年度)によると、通院にかかる費用は1年間で約20万円(薬局での調剤費用を含む)です。1か月で考えると1割負担で1,700円、2割負担で3,400円、3割負担で5,200円程度です。
この金額は目安のため、現在病院へ通っている方は実際の費用を計算してみましょう。病院での診療費に加え、通院のための交通費や、仕事を休んでご家族が付き添う場合、ご家族の負担も考慮する必要があります。通院より訪問診療の費用の方が高くなることがほとんどですが、通院のための移動時間と待ち時間、交通費がかからなくなるメリットがあります。
訪問診療と「入院」の費用面での違い
生命保険文化センターの統計によると、入院時の自己負担費用の平均は15〜30日で28万4,000円、30〜60日で30万9,000円※となっています。
※高額療養費制度を利用した場合は利用後の金額で計算。
※治療費に加え、食事代、差額ベッド代、交通費、日用品費などを含めて計算。
入院と訪問診療を費用面で比較した場合、入院の方が高くなる場合が多いです。入院ではなく訪問診療を検討する場合は、医療費だけでなく介助の負担や必要な設備の導入費用を考慮してください。
基本的な訪問診療の費用の計算方法
訪問診療の費用は、以下の式で算出されます。
訪問診療の費用=【基本診療費 + 加算される診療費】 × 負担割合(1〜3割)
基本診療費は主に以下の3つを合計した金額になります。
- 訪問診療料
- 在宅時医学総合管理料
- 居宅療養管理指導料
基本診療費は厚生労働大臣が定める施設基準を満たしているかどうかや、訪問の回数、同じ場所で訪問診療を受ける人数によって変わります。
加算される診療費は、血液検査や尿検査などの検査費用や、定期訪問以外で緊急に往診を依頼した場合など、医療行為に応じて変わります。
訪問診療には医療保険が適用される
自宅や施設で療養していて通院が困難な場合など条件を満たせば、訪問診療には医療保険が適用されます。医療保険の対象となるため、医療費負担割合に応じた金額がかかりますが、費用の負担が大きくなりすぎない仕組み(高額療養費制度)があります。
実際の負担金額は「医療費負担割合」によって変わる
訪問診療は医療保険の負担割合によって負担金額が変わります。負担割合は年齢によって以下のように定められています。
6歳未満 2割
6歳から69歳 3割
70歳から74歳 2割※
75歳以上 1割※
※70歳以上でも、現役並みの所得がある方は3割負担。
訪問診療の負担金額は、1割なら7,000円、2割なら14,000円、3割なら20,000円程度が相場です。医療保険以外にも、指定難病の方や自立支援医療を受けている方は自治体から補助が出る場合もあるため、くわしい負担金額は医療機関などにご確認ください。
訪問診療の料金が「高い」場合に使える制度
訪問診療の料金が高い場合、月ごとや年ごとの自己負担金額に応じて以下の制度が利用できます。
- 高額療養費制度
- 医療費控除
それぞれ対象となる費用や、期間、補助金額の計算方法などが違い、基本的にご自身で手続きをする必要があります。
高額療養費制度
高額療養費制度とは、月毎(毎月1日から末日まで)の医療費が上限をこえた場合に、申請することでこえた額を支給してもらう制度です。
以下のように、所得に応じた医療費の上限額の計算式があります。
69歳以下の方のひと月の上限額(世帯ごと)
- 年収約1,160万円~ 252,600円 + (医療費-842,000) × 1%
- 年収約770~約1,160万円 167,400円 + (医療費-558,000) × 1%
- 年収約370~約770万円 80,100円 + (医療費-267,000) × 1%
- ~年収約370万円 57,600円
- 住民税非課税者 35,400円
70歳以上の方のひと月の上限額(世帯ごと)
- 年収約1,160万円~ 252,600円 + (医療費-842,000円) × 1%
- 年収約770万~約1,160万円 167,400円 + (医療費-558,000円) × 1%
- 年収約370万~約770万円 80,100円 + (医療費-267,000円) × 1%
- ~年収約370万円 57,600円
- 年収156万~約370万円 個人ごと18,000円 世帯ごと57,600円
- Ⅱ 住民税非課税世帯 個人ごと8,000円 世帯ごと24,600円
- Ⅰ 住民税非課税世帯 個人ごと8,000円 世帯ごと15,000円
※この医療費には入院時の食費や差額ベッド代等は含みません。
過去1年以内に3回以上、上限額をこえた場合、4回目からは上限額が下がります。高額療養費は、加入している医療保険(健康保険組合・協会けんぽなど)に、支給申請書を提出することで支給されます。支給まで、受診した月から少なくとも3カ月かかりますので注意してください。
高額な窓口支払いが負担となる場合、事前に限度額適用認定証を申請して交付されれば、自己負担限度額までの支払いでよくなります。現在は、マイナ保険証で「限度額情報の表示」に同意すれば、支払いの時点で自己負担限度額までとすることもできます。
医療費控除
医療費控除とは、1年間(1月1日から12月31日までの間)に支払った医療費が所定の金額をこえた場合に、確定申告を行うことで所得控除される制度です。
控除額の計算方法
「支払った医療費の総額 − 保険金などで補てんされる金額 − 10万円=控除対象額」
上記の額が、所得から控除されることで、所得税や住民税が減り、払いすぎた所得税の還付、住民税の減額という形で医療費負担が軽減されます。
対象となる金額は高額療養費制度とは異なり、訪問診療で請求された交通費や入院の際の食事代も対象です。
対象となる代表的な費用は以下の通りです。
- 病院・訪問診療の診療費
- 医師の処方箋にもとづく医薬品の調剤費
- 入院費(差額ベッド代は除く)
- 治療に必要な医療器具の購入費(松葉づえなど)
- 通院や訪問診療に必要な交通費
- 歯の治療費(保険適用外の費用を含む)
- 治療のためのリハビリ・整体費
- 介護保険の対象となる介護費
医療費控除では、自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のための医療費も対象となり、合算が可能です。
医療費控除について必要な書類などはこちらの記事でくわしく解説しています。
>>
費用面を考慮して必要なサービスを選ぶようにしよう
訪問診療の料金は、通院に比べると高くなる場合が多いです。反対に、入院と訪問診療の費用を比べると、入院の方が高くなる場合が多いです。受けられる医療サービスや家族の介護負担、患者さん自身の希望なども含めた判断が必要になります。
訪問診療の費用は医療保険の対象となり、高額になった場合は高額療養費制度や、医療費控除を使うことで、負担を軽減することができます。
費用を考慮したうえで、ご家族の状況に合った医療サービスを選びましょう。